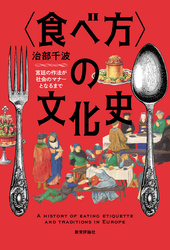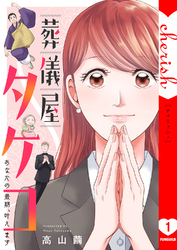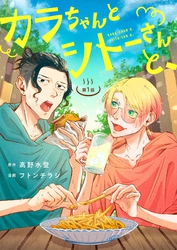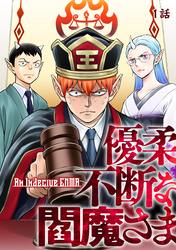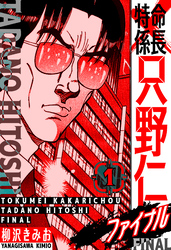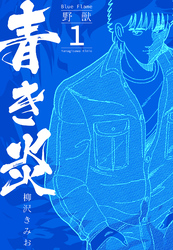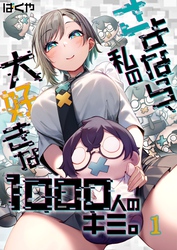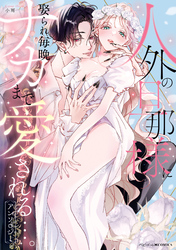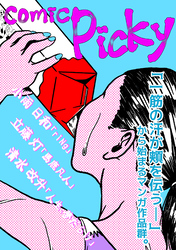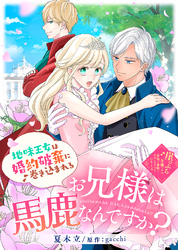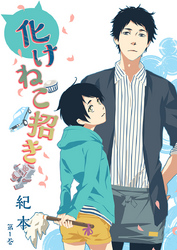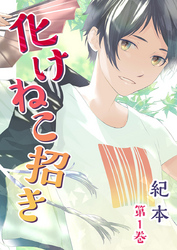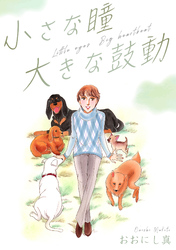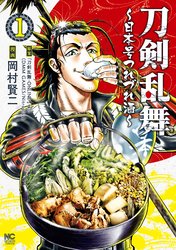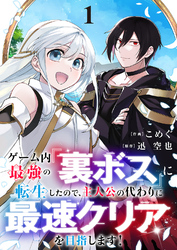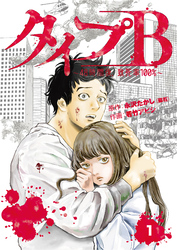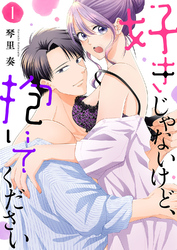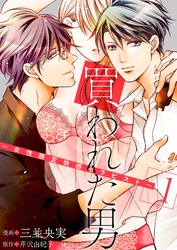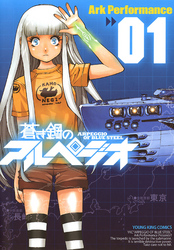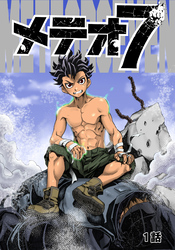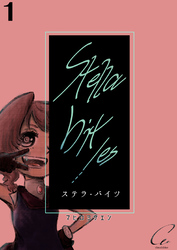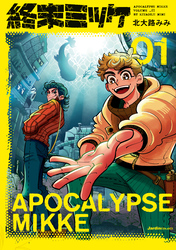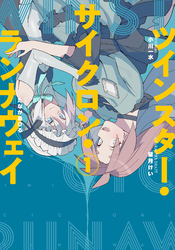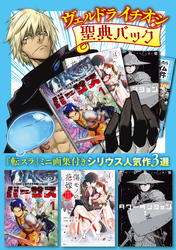〈食べ方〉の文化史—宮廷の作法が社会のマナーとなるまで
あらすじ/作品情報
手づかみからナイフとフォークを使った食事への移行は、近世以降のできごとである。カトラリーの使い方、料理の切り分け、配膳、給仕の方法……ヨーロッパの人びとは〈食べ方〉をどのように変化させていったのか。宮廷の饗宴からレストランでの食事、庶民の会食にいたるまでその歩みを追う。食べるという行為は、単に生命を維持するための栄養摂取にとどまらない。どのように食べるか、ということを我われ人間は考えてきた。テーブルの前に置かれた椅子に座り、ナイフとフォークを使って行儀よく食べるという、現代で当たり前となっている食事の光景は、ヨーロッパで長い年月のあいだに形成されたものである。王を中心とした宮廷という社会で、ほんの一握りの人びとが築き、特権的に受け取ってきた文化は、近代に入り、より身近なものとなった。そして今、現代に生きる我われも、それを享受している。『〈食べ方〉の文化史』と題する本書では、古代から近代にかけて、時代とともに変わっていく食の環境を追いながら、ヨーロッパの人びとの「食べ方」についてみていく。どのような場所で、なにを、どのようにして食べたのだろうか。また、人びとにとって、食べるとはどういうことであったか ― 本書の旅は、こうした問いから始まる。宮廷の饗宴を中心に、食が文化へと昇華した歩みを、一緒にたどっていただければ幸いである。(「はじめに」より) 【目次】第1章 古代から中世におけるヨーロッパの食第2章 ルネサンスと食 ⎯⎯ イタリアで始まる新時代の幕開け第3章 フランス絶対王政下の食と作法 ⎯⎯ オート・キュイジーヌの誕生第4章 十九世紀における食のかたちと習慣 ⎯⎯ 新しい社会の礼儀第5章 宮廷文化の継承と東洋への広がり